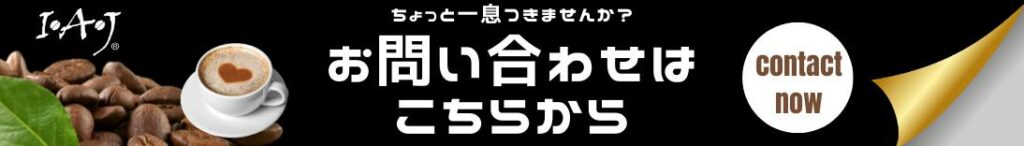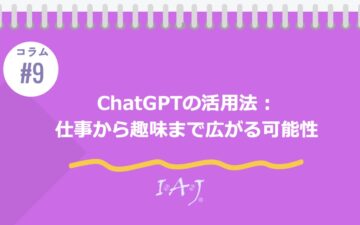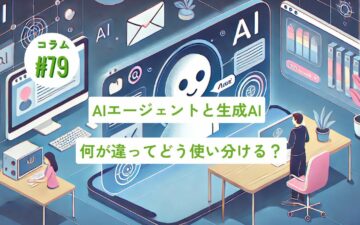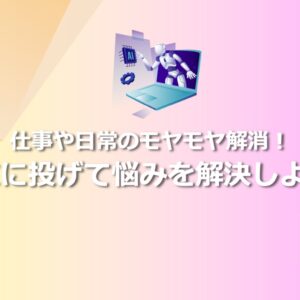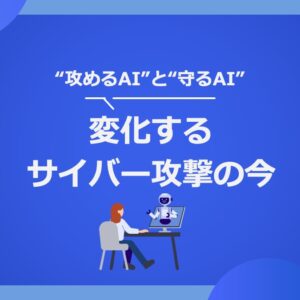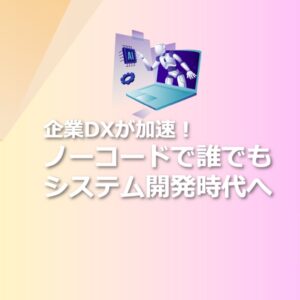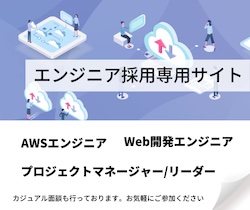1. データ連携の話
中小規模のSaaSサービスが増える中で、「他のサービスとどうやって連携するか?」という課題に直面することが多くなっています。特に業務システムや顧客管理ツールと連携したいというニーズは強く、連携設計はサービスの価値を左右するといっても過言ではありません。でも、そんなに難しく考えなくても大丈夫です。ここでは、少しだけ視点を変えることで見えてくる“ちょうどいい”データ連携設計の考え方をお届けします。
2. データ連携の「目的」をはっきりさせる
最初に考えるべきは、「何のためにデータを連携するのか」です。例えば、顧客情報を一元管理したいのか、他システムからの受注情報を自動で取り込みたいのか。それぞれ目的が違えば、必要な連携方式も変わってきます。「目的ファースト」で考えることが、無駄のない設計への第一歩です。
3. 連携方式はシンプルが基本
中小規模SaaSの場合、運用やコストを考えると「できるだけシンプルに」というのが基本のスタンスになります。例えば、REST APIによるデータ連携は比較的シンプルで柔軟性が高く、構築・運用コストも抑えられます。リアルタイム性をそこまで求められないなら、バッチ連携(CSVファイル等)もまだまだ現役で活躍できます。
4. セキュリティと運用性のバランスを取る
API連携をする際は、セキュリティ対策が必須です。APIキーやトークンの取り扱い、アクセス制限、暗号化などの基本は押さえておきましょう。とはいえ、過剰な設計をしてしまうと、使い勝手が悪くなったり運用が煩雑になることも。現場の運用に合わせた「ちょうどよさ」が大切です。
5. 「スキーマ設計」は未来への投資
データ連携でよくある落とし穴が、スキーマ(データの設計)を適当に済ませてしまうことです。最初は数項目だったとしても、あとから「住所も入れたい」「取引履歴もほしい」と拡張したくなるのが常。今だけでなく、将来の拡張性も見据えたスキーマ設計をしておくと、あとあと楽になります。
6. SaaSならではの制約を逆手に取る
中小規模SaaSの多くは、リソースやカスタマイズ性に限りがあります。でもそれは「制約」であると同時に「設計のヒント」にもなります。例えば、「Webhookしか使えない」という仕様なら、「じゃあ受信側で柔軟に処理できるようにしよう」と発想を転換することができます。制限があるからこそ、無駄のない設計が生まれるのです。
データ連携設計において大切なのは、「理想を追いすぎないこと」。中小規模のSaaSでは、使いやすく、維持しやすく、きちんと目的を果たせることがなによりも重要です。凝った仕組みより、現場でちゃんと使われる仕組みこそが価値になります。地に足のついた設計を心がけて、SaaSの可能性を広げていきましょう!

<<IAJってどんな会社?>>
創業以来25年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。
おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。
私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。
他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?