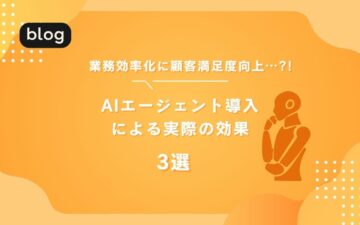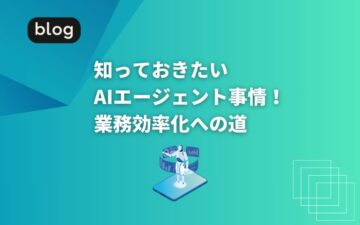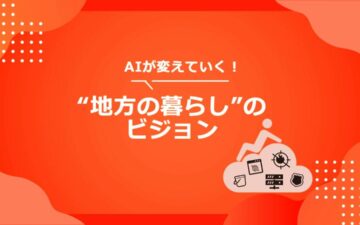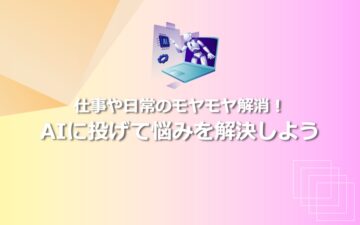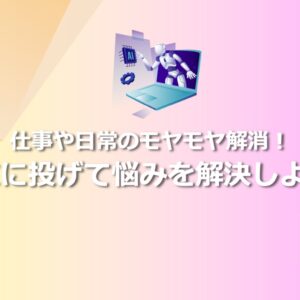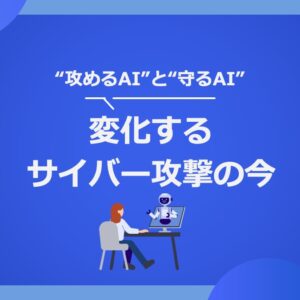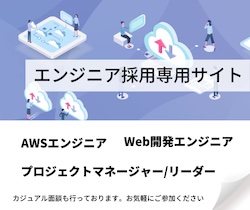10代が高い利用率を誇るTikTokでは、正しくない情報を含む動画が多く確認され、そうした動画の総再生回数が3億回を超えるとも言われています。その動画を見た子供の内、どれだけの子がフェイクニュースだと見抜くことができたのでしょうか?
近年AIの発達で精巧な誤情報も出回ることが増え、これからの教育においては情報をただ受け入れるのではなく、それを正しく評価する力が求められています。現代を生きる子供たちは、どのようにしてこの力を身につけことができるでしょうか?本記事では、AIと教育について考えていきたいと思います。
この記事では、AIと共に生きる世代の子供たちに対する教育の現状や将来についてお話していきます。
【AI活用】ご検討されている方はこちらへ >>
・子育て世代の方
・日常で子供に関わられている方やお仕事をされている方
・AIと教育について関心のある方
AIと生きる子供の現状と必要な「見抜く力」とは
現代の子供たちは、AIと密接に関わる環境で育っています。教育現場でもAI技術が導入され、日常生活でもAIが便利な道具として使われています。しかし、AIが引き起こす影響は良い面ばかりではありません。
この段落では、世界や日本でのAI教育の現状と、子供たちに求められる「見抜く力」について見ていきましょう。
◇AI時代の子供たち — 日本と世界の現状
AIが子供たちに与える影響は、国によって取り組み方に差があり、特に日本では課題が多い状況です。
かたや世界では、AI教育の重要性を認識した国々が早い段階から取り組んでおり、教育機関でのAIプログラムが進行中です。フィンランドをはじめ、他の北欧諸国では、AI教育を学校カリキュラムに組み込む動きが加速しています。
【フィンランド】フェイクニュースに流されない教育を実践!
フィンランドではAIに関する教育が早期から行われており、子供たちに情報リテラシーを教えるための特別なプログラムが導入されています。「批判的思考の育成」や「フェイクニュースの事例研究」など、学校教育の一環として取り入れられ、子供たちは情報の信頼性を評価する能力を身につけています。プログラムを通して、AIをどのように使いこなすかだけでなく、AIが生成する情報の正確性を判断する方法についても学んでいます。
参照元:How Finland Is Teaching a Generation to Spot Misinformation
◇AIが子供に与える良い影響と悪い影響とは?
AIは子供にとって、進捗に合わせた個別学習のサポートが可能です。例えば、AIは各生徒の学力に合わせて問題を出題し、個別対応ができます。子供たちの学習を支援する強力なツールである一方、AIへ過度に依存すると思考力の低下を招く可能性があります。AIの解答をそのまま受け入れることは、批判的思考を育む機会を減らし、思考の幅を狭める恐れがあるからです。
日本の教育現場では、AIによって与えられる情報が必ずしも正確でないこともあり、AIに依存しすぎないよう注意が必要とされています。
◇子供たちに必要な「見抜く力」とは?
AIの情報を適切に評価し、正確な判断を下すために欠かせない能力が「見抜く力」になります。特にSNSや検索エンジンを多用する現代では、正しい情報を選び取る力が求められます。
AIが生成する情報やSNS上のコンテンツは、正確性が保証されていない場合が多いため、子供たちはこれらの情報を鵜呑みにせず、真偽を見極める力を身につけることが必要不可欠です。AIに対する教育の進んだ北欧諸国では、誤情報に対する批判的な視点を養うためのプログラムが採用されており、こうした教育が「見抜く力」の養成に寄与しています。

日々流れ込んでくる大量の情報に対して、ただ鵜呑みにするのではなく、「これは本当か?」という視点を持つことは大事ですね!
AIと共存するには?「見抜く力」の育て方3選
AIを活用することで学びが深まる一方、情報の信頼性を見極める力も養う必要があります。AIと共存し、誤情報に惑わされず、正しい情報を選び取る力を育てるためには、教育現場や家庭での実践的な取り組みが重要です。
この段落では、AIを活用した教育法や家庭でできる取り組みを3選ご紹介します。
その1:情報リテラシー教育の重要性とアプローチ
AIを正しく使いこなすためには、情報源を批判的に評価し、誤った情報を選別する能力を養う必要があります。AIによって膨大な情報が手に入る現代において、その情報が正しいかどうかを「見抜く力」はさらに重要になります。
日本でも情報リテラシー教育は今後ますます必要になると考え、文部科学省は教育現場でのAIリテラシーの導入を進めています。
情報リテラシーの向上が必要と感じている
アメリカのPew Research Centerが2021年に実施した調査によると、インターネットユーザーの大多数が、オンライン情報の信頼性を確認する方法を学びたいと考えていることが示されました。
この調査では、特に若年層が情報リテラシーを向上させる必要があるという結果が出ており、教育機関が重要な役割を果たすことが明らかになっています。
参照元:The State of Digital Literacy in America
その2:AIを活用した実際の教育プログラムや教材
AIを活用することで、学習内容を個別化し、学生一人ひとりに合わせたフィードバックを提供できます。
例えば、「Khan Academy」は、AIを活用して生徒一人ひとりの進捗に合わせた問題を出題し、間違った解答に対しては補足説明を加えるなどのフィードバックを提供します。このプロセスによって、生徒は自分の間違いを理解し、問題解決能力を高めることが可能です。
学習プラットフォーム「Coursera」では、AIを使って学習者の理解度に基づいたカスタマイズされた教材を自動的に提示し、最適な学習パスを提供します。このようなパーソナライズドな学習体験により、生徒は情報を正確に判断する能力を高め、必要な情報を見抜く力を養うことができます。
その3:家庭でできるAIとの向き合い方
家庭でも親が積極的に子供と一緒に情報を評価する活動を行うことで、子供たちはAIに対する適切な態度を学びます。親が情報源をチェックする方法を教えることは、子供が誤情報を見抜く力を育てる上で重要です。
【見抜く力】AIとの健全な向き合い方を直接伝える
Common Sense Mediaによる調査では、親が子供にインターネットやAIをどう使うかを教えることで、子供たちがメディアに対してより批判的な視点を持つようになると報告されています。親子でメディアの内容を一緒にチェックし、情報の信頼性を確認することが、情報リテラシーを育むために効果的だとされています。
参照元:Parenting in the Digital Age
子供も大人も危険!SNSとAIによる誤情報の拡散
SNSやAIは現代の情報流通に欠かせないツールですが、その一方で誤情報が拡散されやすい環境でもあります。特に若年層は、SNS上のフェイクニュースに影響を受けやすく、AIが生成した内容に対しても無批判で接することが問題視されています。
この段落では、誤情報の拡散状況と、それが子供たちや大人に与える影響について考察します。
◆SNSとAIが生む誤情報の実態とその拡散
🚨10代後半の2人に1人が利用!身近なSNSに潜むフェイクニュース
TikTokにおける「誤情報の拡散」についてNHKが行った調査によると、誤情報が含まれる動画は総再生数が3億回を超え、特に健康関連の虚偽情報が多く見られました。誤ったダイエット方法やワクチンに関する不正確な情報、さらに命に関わる嘘の情報まで拡散され、これらの誤情報は数百万回の再生回数を記録しました。拡散された誤情報を含む動画の一部は、再生数が200万回を超え、急速に広がった報告もされています。このような拡散がもたらす社会的影響に対し、SNSプラットフォームでの対策が急務であることが指摘されています。
参照元:【独自検証】TikTokにあふれる誤情報… 総再生数は3億回超に
◆SNSが子供たちに及ぼす影響とは
誤情報が子供たちに与える影響は心理的・社会的に大きく、信じ込むことで誤った認識を形成する恐れがあると言われています。何故なら、SNSを頻繁に使用する若年層は誤情報を信じやすい傾向があり、その結果として社会的な不安や誤解が生じることがあるためです。また、SNSで拡散される誤情報は、特に健康や社会的な問題に関する誤った認識を生み出し、その後の行動に影響を与えることが多い傾向にあります。
◆子供だけの問題ではない!大人も騙される危険性
誤情報は、子供のみならず大人にとっても深刻な問題です。
実際、アメリカで行われた調査では、SNSを頻繁に利用する成人のうち約7割が誤情報に触れた経験があると報告されています。健康や政治に関する虚偽の情報が特に多く、社会的にも大きな影響を及ぼすと言えます。
例えば、COVID-19に関する虚偽の情報や、ワクチンに対する誤った認識が広がったことがあり、これが一部の人々にワクチン接種を避けさせる結果となりました。これらの誤情報は、ただの個人の信念にとどまらず、社会全体に影響を与える可能性が高いのです。加えて、AI技術を使った「ディープフェイク」技術の進化により、見た目がリアルな偽の映像や音声が拡散されやすくなり、ますます信じやすくなっています。

誤情報が社会に与える影響を最小限に抑えるためには、メディアリテラシーを向上させることが急務のようです!
日本のAI教育の現状とこれから
日本でもAI技術の進化に伴い、教育現場でもAIを活用した学びが広がりつつありますが、実際にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
この段落では、政府や教育機関のAI教育に関する現状と今後の方向性を探り、AI教育が子供たちに与える影響についてお話したいと思います。
◇日本で進むAI教育の具体的取り組み
日本政府は、AI技術が今後の社会において中心的な役割を果たすと認識し、AI教育を学習指導要領に組み込み、教育の充実を図っています。特に、AI技術を活用した社会的な役割や未来の仕事に向けた準備として、学校教育でのAIリテラシー教育が強化されています。
JST(科学技術振興機構)や企業との連携も!広がるAI教育
文部科学省は、2024年に発表した「未来の学びをデザインする」という方針の中で、AIやデータサイエンスの教育の重要性を再確認し、小中高の各段階でAIに関連する教育内容を積極的に取り入れることを掲げています。この方針に基づき、2024年からはAI教育が学習指導要領により具体的に実施され、特に小学校でのプログラミング教育やAI技術を用いた学習支援ツールの導入が加速しています。また、JSTや企業との連携により、AI教育の教材やカリキュラム開発が進められています。
参照元:初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン
◇AI教育における課題と今後の方向性
日本のAI教育は進展していますが、地域間の格差や教師のスキル向上といった課題が依然として存在し、これらの解決が今後の重要な課題となります。
地域差によって生まれる教育格差
The Japan Times(2023)によると、AI教育の導入は地域によって異なり、都市部と地方では教育の機会に差が出ているという問題が確認されています。特に、地方の学校ではAIに必要なインフラや教材が不足しており、これが教育の格差を生んでいます。また、教師に対するAI研修やトレーニングも十分でなく、これが教育効果を制限する要因となっています。
参照元:Generation AI: Education reluctantly embraces the bots
◇【AIと人間の共生】未来の教育に向けて
AIはあくまでツールに過ぎません。子供たちがAIを適切に活用するためには、AIに依存せず、独自の創造性や問題解決能力を養うことが大切です。また、人間性を重視した教育が今後のAI教育において重要な要素となるでしょう。
人間らしさを保ちながらAIと共生する力
OECD(経済協力開発機構)の2023年の報告書によると、AIと人間の共生を目指す教育が求められています。特に、AIが進化する中で、創造性や批判的思考、感情の理解といった『人間らしい能力』の重要性が再認識されています。教育システムは、これらの能力を育む方向にシフトする必要があるとされています。
参照元:OECD Digital Education Outlook 2023

AIの恩恵を受ける一方で、人間らしい創造力や感情を理解する力などがなかなか育つのに簡単ではない世の中になってきていないでしょうか?「人間らしさ」を改めて考えるのに良い機会かもしれません。
【まとめ】AI教育と未来の学び

AI教育は、未来の社会を生きるために必要不可欠な要素として、今後ますます重要になってきます。
これまで紹介した内容を総括し、今後の教育におけるAI活用の方向性や課題について、改めて整理していきます。
▶︎ 日本のAI教育の現状と未来のビジョン
▶︎ AI教育における課題と解決
▶︎ 未来の教育におけるAIと人間の共生
【AI導入サポート】IAJにおまかせ!こちらからお気軽にお問合せください >>
よくある質問と回答
- 子供がAIに依存しすぎることを防ぐにはどうすればよいですか?
-
AIを補助的なツールと認識させた上で使うことが重要です。子供は自ら考えて問題解決の能力を養うことが必要なので、親や教師がAIの使い方をガイドし、批判的思考や独立心を育てるような教育を行うことが大切になります。
- AIが生成する情報をどのように見抜くべきですか?
-
情報の正誤性を見抜くためには、情報源を確認し、複数の信頼できるソースから情報を得ることが大事です。また、AIの出力が偏っていないかを意識し、常に批判的に考えることが「見抜く力」を養うためには不可欠です。
- 将来、AIが教育をどのように変えると予測されますか?
-
AIは教育の個別化をさらに進め、学習の進捗に応じて教材を自動的に調整することができるようになります。また、AIは教師のサポートツールとしても大きな役割を果たし、学習効果を高めるためにデータ分析にも活用できると考えます。
最後に…
AI時代の子供の現状や影響、共生するための「見抜く力」、今後の日本の教育などについて振り返ります。

AIと生きる子供たちへ、格差のない環境や教育を提供することが大人の使命ですね。
日々の生活の一部になっているSNS。目に入る物すべてを疑う必要はありませんが、“良い情報” が全部正しいわけではなく、自分の中での物差しやセンサーを持つことが大切だと感じました。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!

<<IAJってどんな会社?>>
創業以来24年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。
おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。
私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。
他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?