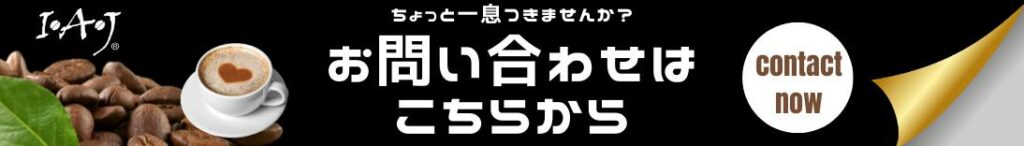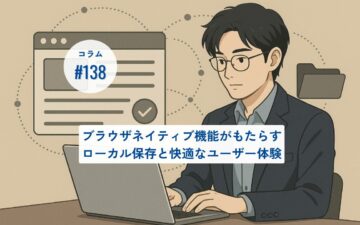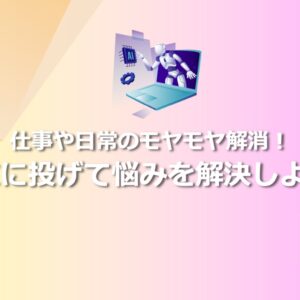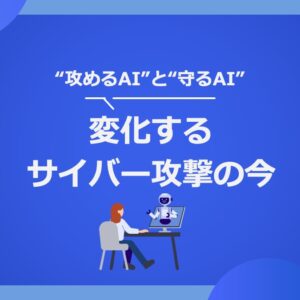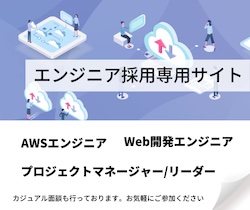1. データ活用のジレンマ
ここ数年、「データ活用」がビジネスの中心にあることは言うまでもありません。AIやマーケティングなど、多くの分野で学習には大量のデータが必要です。一方で、プライバシー保護に対する社会の目も厳しくなってきております。そのため、私たち開発者には「ただ動くものを作る」だけでなく、「どのように守るか」という視点も同時に設計へ組み込む責任があります。
たとえば、顧客データを活用するプロジェクトでは、分析や最適化のために個人データを扱うことが多いですが、「どこまでやっていいのか」「ユーザーにどう説明すれば納得してもらえるのか」といった、ちょっと難しい倫理的な判断も必要になります。
2. データクリーンルームがもたらす“安心感”
そんな中で注目されているのがデータクリーンルームです。名前だけ聞くとクリーンルーム(無菌室)みたいですが、ITの世界では「プライバシーを守りながらデータ分析ができる環境」のことを言います。
たとえば、広告会社と小売業が連携して広告効果を測定したいとき、クリーンルームを使えば、生データを直接やり取りすることなく、安全な空間の中で突合や集計処理ができます。しかも、ユーザーごとの情報がそのまま見えるわけではないので、情報流出のリスクも抑えられます。
この仕組み、エンジニアにとってもありがたい存在です。というのも、セキュリティや匿名化の処理を全部自前でやる必要がなく、あらかじめ設計された仕組みに乗ることができるからです。
3. プライバシー保護設計は後付けできない
ただし、気をつけたいのは「セキュリティはあとで考えればいいや」では、もう通用しないということです。
今では「Privacy by Design(設計段階からのプライバシー保護)」という考え方が当たり前になりつつあります。
例えば、以下のような点が挙げられます:
こういったポイントを、開発の最初の段階からチームで共通認識として持っておくことが大事です。
4. エンジニアに求められる“倫理的感覚”
開発者は、技術力が評価されがちですが、これからの時代はそれだけじゃ足りません。特に、個人情報を扱うようなシステムでは、「この実装って本当にユーザーのためになってる?」と考える倫理的な視点がますます重要になっています。
私のチームでは、レビュー時に「このログ出力にユーザーIDは本当に必要か」「氏名が平文で出力されていないか」といったチェックを丁寧にしています。法律を守るのはもちろんですが、ユーザーからの信頼を得ることこそが、サービスの価値を左右します。
5. クリーンな設計で信頼されるシステムへ
最終的に、どれほど高度な機能を持ったシステムであっても、ユーザーから「このサービスは不安だ」と感じられてしまえば、使ってもらうことはできません。逆に、「このサービスは安心して利用できる」と感じてもらえれば、競合との差別化にもつながります。
データクリーンルームのような技術は、開発者にとって心強い味方です。ですが、それだけに頼るのではなく、最初から「守る設計」を意識することが、これからの開発のスタンダードになっていくと思います。
これからのシステム開発では、「使えるかどうか」だけでなく、「信頼されるかどうか」がより重視されていくでしょう。プライバシー保護を設計の中にしっかり組み込んでいくことで、開発者として社会と信頼関係を築くことができると考えています。「安心して使えるサービス」を、私たちの手で作っていきましょう。

<<IAJってどんな会社?>>
創業以来25年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。
おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。
私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。
他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?