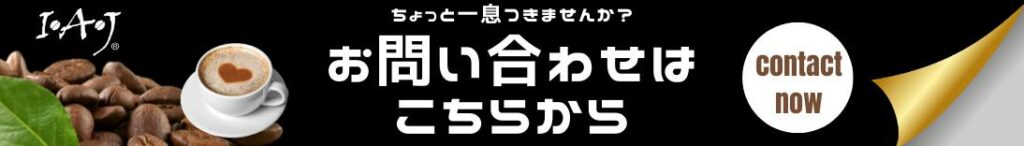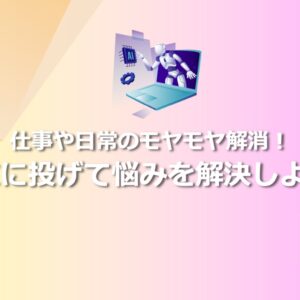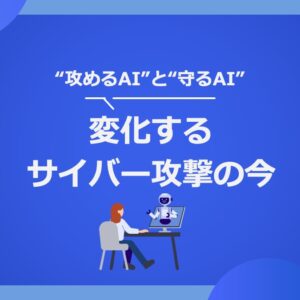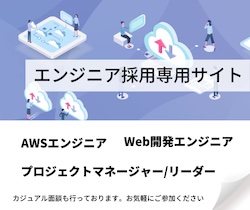2025年、生成AIの進化は動画制作の常識を大きく変えています。私たちシステムエンジニアにとっても、この変化は無視できないものとなっています。今回は、最新の動画生成AIの動向と、それがもたらす可能性についてお話しします。
1. テキストから動画へ:Veo 3の登場
Google DeepMindが開発した「Veo 3」は、テキストや画像のプロンプトから高品質な動画を生成するAIツールです。従来のVeo 2と比較して、動きの精度、リップシンクの品質、映像のリアリズムが大幅に向上しています。さらに、リアルな環境音や対話の生成、複雑なプロンプトから物語性のあるクリップを作成する能力も備えています。
2. クリエイターのための新ツール:Flowの導入
Googleは、Veo 3と連携する新しいツール「Flow」を発表しました。Flowは、テキストや画像のプロンプトから8秒の短い動画クリップを生成し、それらを組み合わせてシーンを構築することができます。これにより、クリエイターはアイデアを迅速に可視化し、映像制作の初期段階を効率化できます。
3. OpenAIのSora:リアルな映像生成の可能性
OpenAIが開発した「Sora」は、テキストからリアルな映像を生成するAIモデルです。ユーザーが簡単なテキストプロンプトを入力するだけで、非常にリアルな映像を生成できるこのツールは、映像制作の多くの部分を担える可能性を示しています。現在は限定的な公開となっていますが、その精度とリアルさが注目を集めています。
4. ビジネスへの応用と新たな可能性
動画生成AIの進化は、ビジネスの現場にも大きな影響を与えています。マーケティング、教育、エンターテインメントなど、さまざまな分野での活用が進んでおり、効率的なコンテンツ制作や新たな表現方法の開拓が期待されています。また、企業のブランディングやプロモーション活動にも、動画生成AIが新たな価値を提供しています。
5. 技術者としての視点:生成AIとの向き合い方
私たちシステムエンジニアにとって、生成AIの進化は新たな挑戦でもあります。AIが生成するコンテンツの品質や倫理的な問題、著作権の取り扱いなど、技術的な課題と向き合う必要があります。しかし、これらの課題を乗り越えることで、より豊かな映像体験を提供できる可能性が広がっています。
2025年の動画生成AIの進化は、映像制作の新たな時代を切り開いています。私たち技術者も、この変化を積極的に受け入れ、活用していくことで、より魅力的なコンテンツを生み出すことができるでしょう。生成AIとの共創が、未来の映像体験を豊かにする鍵となるのです。

<<IAJってどんな会社?>>
創業以来24年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。
おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。
私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。
他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?