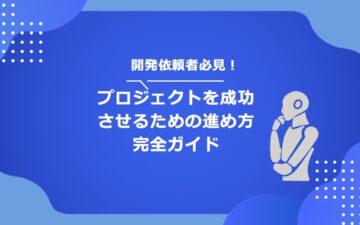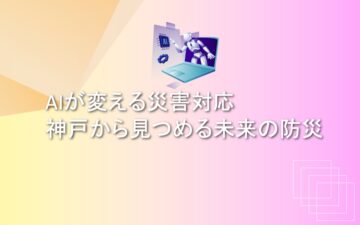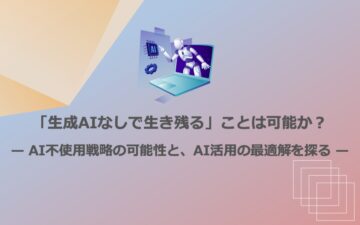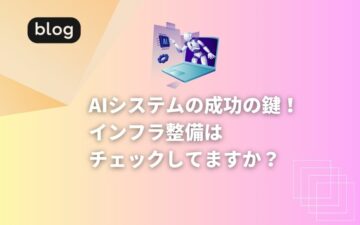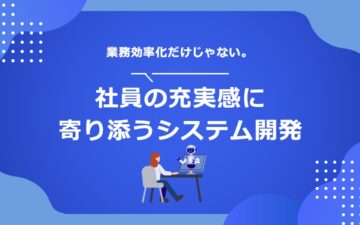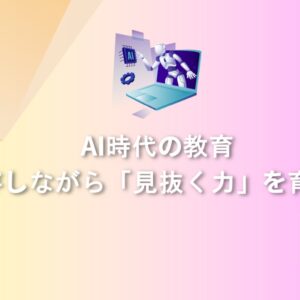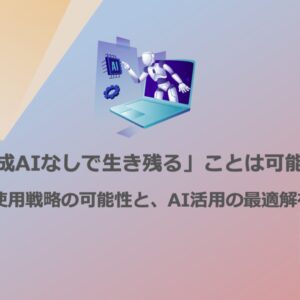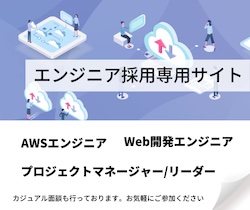AIが、私たちの生活を豊かにする可能性を秘めていることはよく知られています。
反面、様々なリスクをはらんでいることはどのくらい認識されているでしょうか?
今、至る所でAI技術の恩恵を受けられる環境と言えますが、今回はAI生成物について、メリットやそのリスクにも目を向け、安全な活用法について考えていきたいと思います。
この記事では、「生成AI」を使って作る文章や画像、動画などの生成物の便利な点や活用例、使用にあたって気を付けるべき点についてお話しています。
【AI活用】ご検討されている方はこちらへ >>
・生成AIってよく聞くけど、まだ馴染みがない方
・画像や音楽を自分で簡単に作ってみたい方
・便利だからAIは使いたいけど、リスクが気になるという方
・AIを業務や創作活動へ利用することに興味がある方
AI生成物を使うメリットとは?事例3選
AIは今や私たちの生活や仕事の中で欠かせないツールになりつつあります。
その中でも、AIが生成する “文章/テキスト” や “画像”、“音声”、“音楽”、“動画” といった「生成物」は、効率化と創造性の面で大きなメリットをもたらします。
この章では、それぞれの生成物がどのような利点を持っているのかを具体的にお伝えします。
【IAJ】AI技術の導入をお考えの方へ。詳しい事例はこちら >>
例1◆文章(テキスト)生成で時間を節約!
AIによるテキスト生成は、文章作成にかかる時間を大幅に短縮できます。
チャットボットやAIライティングツールを使うと、下書き作成やアイデア出しを瞬時に行えるため、プロセス全体の効率が向上します。
例えば、「ChatGPT」や「Jasper AI」といったツールは、数秒でブログの概要やメールのテンプレートを作成可能です。これにより、書くことに悩む時間を削減可能です。
例2◆画像生成でクリエイティブな作業がもっと身近に!
現在、“デザイナー”でなくても、AIを使えば手軽にプロ仕様の画像を作成できます。
画像生成AIは、簡単なプロンプトを入力するだけで、イラストや広告素材を即座に生成してくれます。
一例ですが「MidJourney」や「Canva AI」など、初心者でも簡単に操作できるツールにより、SNS投稿用の視覚的に美しい画像を数クリックで作成可能です。これにより、クリエイティブな作業がより身近になります。
例3◆音声や音楽をAI生成でコスト削減!
AIを使うことで、音声や音楽の制作コストを大幅に削減できると考えられています。
従来プロのナレーターや作曲家に依頼していた音声や音楽の制作が、AIによって手軽に低コストで可能になるからです。
例として「Resemble AI」や「Boomy」など、プロのナレーションやオリジナル音楽を生成でき、従来の制作費用と比較して数分の一のコストで提供されます。
特に中小企業や個人プロジェクトで大きな効果を発揮すると言えますね!

AIによって色んな物が『気軽』に『簡単』に『誰でも』作れる時代に!
Amazon社も独自の生成AIモデル(Amazon Nova)を今月発表し、来年以降よりAIによるクリエイティブ制作が加速しそうですね。
知らないと危険!AI生成物に潜むリスク3選
AI生成は便利で非常に魅力的なツールですが、その裏には注意すべきリスクが隠れています。
著作権侵害や偽情報の生成など、知らずに利用すると問題に発展することもあります。
この章では、AI生成物に潜む3つの主要なリスクを具体例を交えながら解説し、それぞれに対する基本的な理解を深めていきましょう。
その1◇著作権侵害の可能性
AI生成物は、著作権侵害のリスクを伴う場合があります。
AIが学習に使用するデータには、許可なく収集された著作物が含まれる可能性があり、生成物が既存の作品と酷似するケースがあるからです。
【著作権侵害】Stable Diffusionに対する訴訟
2023年2月、画像生成AI「Stable Diffusion」を開発したStability AI社が、大手フォトストックサービスのGetty Imagesから著作権侵害で提訴されました。Getty Imagesは、同社の画像が無断でAIの学習データとして使用されたと主張しています。
参照元:ゲッティイメージズ、画像生成AI「Stable Diffusion」開発元を提訴–著作権侵害で
※2024年現在も法廷で闘争中のようです
その2◇偽情報拡散のリスク
AIが生成するテキストや画像は、偽情報として拡散される可能性あります。
AIは現実のデータに基づいて情報を生成しますが、学習データが不完全であったり、曖昧なプロンプトに対して回答を生成する際に、事実とは異なる情報が作られないとは言い切れません。
【フェイク情報の流布】岸田元首相の偽動画拡散
2023年11月、生成AIを利用して作成された岸田文雄首相(当時)の偽動画がSNS上で拡散されました。この動画では、首相に似た声で卑猥な発言がされており、日本テレビのニュース番組のロゴなども不正に使用されています。このような偽動画は、社会的混乱を引き起こす可能性があります。
参照元:生成AIで岸田首相の偽動画、SNSで拡散…ロゴを悪用された日テレ「到底許すことはできない」
その3◇プライバシーやセキュリティへの影響
AI生成物は、プライバシーやデータセキュリティを侵害するリスクがあります。
AIが生成するデータに、学習データから意図せず個人情報が含まれる場合があります。また、生成物を利用する際の不適切な管理が情報漏洩につながる可能性もあります。
【規制法なく野放し】インドの選挙でのディープフェイク使用
2024年のインド総選挙では、政治家がAI生成のディープフェイクを使用して、有権者に複数の言語や方言で個別のメッセージを送る事例が報告されています。
これにより、有権者は高名な政治家から直接メッセージを受け取ったと誤解し、偽情報が広まるリスクが高まっています。
参照元:Indian Voters Are Being Bombarded With Millions of Deepfakes. Political Candidates Approve

生成AIは「簡単」である裏返しとして、利用者は「慎重さ」が求められますね!
【リスク回避】押さえておきたい基本ルール3つ
AI生成物の活用には、便利さと同時にリスクが伴います。
しかし、適切なルールを守ることで、これらのリスクを軽減することができると考えます。
この章では、著作権侵害や偽情報の拡散を防ぎながら、AI生成物を安全に利用するための実践的なルールをご説明します。
ルール1◆生成物の出所を明確にする
ルール2◆偽情報対策ツールを活用する
ルール3◆ 公開前にチェックリストの確認を徹底!

故意でなくても偽情報を世間に広めてしまったり、著作権を侵害してしまう恐れは誰にでもある為、そのリスクを最小限に抑えたいですよね!
AI生成の活用&成功例のご紹介
AI生成物を活用した成功事例は、さまざまな分野で報告されています。
特にコスト削減や効率向上、独自性のあるコンテンツの制作において、AIは大きな力を発揮しています。
この章では成功例を挙げながら、仕事やプライベートでAI生成物を活用する方法について解説しましょう。
成功例1◇企業の広告制作でコスト削減
小規模なEC事業者がAI生成ツールを活用して、広告バナーを自社で制作した事例があります。
この企業では、年間広告制作コストを広告代理店に代わりAIを使うことで大幅削減することができました。
従来外部デザイナーや広告代理店に依頼が必要だった作業を、AIツールに代替することで、低コストかつより自社の意向に沿った広告制作が可能になるかも知れません。
注意すべきポイント💡
AIツールのテンプレートに頼りすぎると、他社とデザインが似通い、ブランドの独自性を損なう可能性があります。適度なカスタマイズでオリジナル度を出しましょう。
成功例2◇動画制作で独自性を高める
あるスタートアップ企業が投資家向けのプロモーション動画をAIツールを活用して制作し、視覚的インパクトでより大きな関心を引き、目標額を超える投資額を調達した例がございます。
AIが提供する高度なエフェクトや豊富なカスタマイズオプションを使うことで、視覚的に魅力的なコンテンツを短期間で制作できるようになっています。
また動画生成ツールをうまく利用できると、企業のブランドイメージ向上の一助にもなりそうです。
注意すべきポイント💡
高度なエフェクトに依存しすぎると、メッセージ性が薄れる可能性があります。
まず、動画の「目的」や「伝えたいこと」を明確にした上で活用することが重要です。
成功例3◇プロの知識不要で音楽制作
音楽生成AIを使った音楽制作が広がっており、YouTubeやコンテンツクリエイターの間では独自のBGMを制作して利用するケースが増えています。プロの知識が必要だった音楽制作が、手軽に、短時間で高品質なトラックが生成できる点で高く評価されています。
AIが簡単にカスタム音楽を生成してくれるので、音楽制作が身近になり、多くのクリエイターがより自分達のコンテンツの創造性を伸ばすことに貢献しています。
注意すべきポイント💡
同じAIトラックが他のクリエイターにも生成される可能性があるため、より高度なオリジナリティを求める場合は追加編集をすることも必要です。
【まとめ】AI生成物を今後うまく利用しよう
ここまでAI生成物の利点やリスク、具体的なツール、成功例などについてお話ししてきました。
AI生成物は、私たちの仕事や生活を便利にする大きな可能性を秘めていますが、その活用には一定のルールや知識が必要です。
これまでの内容を総括し、AI生成物を安全かつ効果的に使うためのポイントを整理します。
AI生成物のメリットを最大化するポイント
取り組むべき具体的なステップ
AI生成物を安全に活用するための心構え
【AI導入サポート】IAJにおまかせ!こちらからお気軽にお問合せください >>

仕事やプライベートで生成AIを使う機会が増えてきています。
リスクについてはあまり考えていなかった、、、と反省あり、今後もどんどん利用しながら慣れて安全に使いこなせるようになりたいです。
よくある質問と回答
- AI生成物は完全にオリジナルと言えますか?
-
AI生成物は、AIが学習したデータを基に作られたもので、完全にオリジナルとは言い切れません。AIは既存データのパターンを学び、それを応用して生成します。
そのため、元となった作品に類似する可能性があります。これを避けるため、生成されたコンテンツが他の著作物に酷似していないか、事前に確認することが重要です。 - AI生成物を仕事で使う場合、事前に確認するべきことは何ですか?
-
仕事でAI生成物を使う場合、まず著作権やライセンス条件を確認することが必要です。
利用するツールの規約をよく読み、商用利用が許可されているかどうかを確認して下さい。
また、生成物の出所や類似性もチェックし、法的リスクを回避する準備をしましょう。 - AI生成物が原因でトラブルになった場合、責任は誰にありますか?
-
AI生成物に関連するトラブルが発生した場合、その責任は生成物を使用した人にあるケースが多いです。ツールを開発した企業が責任を負うことは稀で、使用者が生成物のチェックや利用条件を遵守しているかが問われます。注意深い利用が求められます。
- 今後AI生成物の規制はどうなると考えられますか?
-
現在、各国でAI生成物に関連する規制やガイドラインが整備されつつあります。
特に著作権や偽情報に関する規制が強化される傾向があります。ユーザーとしては、今後の法規制の動向を注視し、常に最新の情報に基づいて利用することが求められます。
まとめ
最後に、AIを活用した生成物のメリットやデメリット、リスク回避策などについて振り返ります。

今回は「生成AIを使う」ことについて入門的なお話をさせていただきました。
記事を書くにあたって初めて音楽をAI生成してみましたが、一瞬でプロ並み⁉️の曲が作れ、簡単すぎて驚きました、、ハマるかもしれません(笑)
これから世代を問わず「生成AIを使う」が当たり前になる時代に向かって、手始めに何か試してみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました!

<<IAJってどんな会社?>>
創業以来24年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。
おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。
私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。
他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?